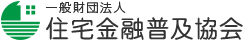改正民法(債権法)では、改正前民法における特定物売買の目的物に瑕疵が存在した場合の瑕疵担保責任(改正前民法570条・566条)の規定が見直され、契約不適合責任へと変わることになります。
1. 改正前民法の瑕疵担保責任
改正前民法では、売買物件に「隠れた瑕疵」が存在する場合は、売主は瑕疵担保責任を負うものとされ、瑕疵担保責任の内容は、
- 原則として損害賠償
- 例外的に契約の目的を達しない場合に限り契約の解除
の2つが認められるというものでした。瑕疵担保責任に基づく損害賠償も契約の解除も、いずれも売主が無過失の場合であっても発生するものとされています。このような瑕疵担保責任という概念が認められた理由は、土地・建物売買契約のように、契約の目的物がいわゆる「特定物」であるからです。売主の債務は特定物である当該土地と当該建物を引き渡すことですから、たとえ、土壌汚染のある土地や雨漏りのする建物を買主に引き渡したとしても、売主は、自己の債務を履行しており、売主に債務不履行はないと考えられてきたからです。
そうすると、売主は、瑕疵のある土地・建物を引き渡したとしても、売主としての債務は履行したことになり、債務不履行責任を負わないことになりますが、そのような結論は、瑕疵のある土地建物を引き渡す売主と、瑕疵の存在を知らずに売買代金を支払う買主との間に経済的な不公平を生ずることになります。このために、法が特別に定めた責任(法定責任)として設けられたのが瑕疵担保責任です。
瑕疵担保責任は、売買当事者の不公平を是正するために法が特別に定めた責任ですから、売主に責めに帰すことのできる事由は必要ではありません。その故に、瑕疵担保責任に基づく損害賠償も契約解除も売主が無過失であっても発生することになりますし、債務不履行責任の場面ではないので、契約の解除は契約の目的が達成できない場合に限り認められています。また、瑕疵が「隠れた」ものでない場合は、あえて法定責任を認める必要もないと考えられます。ただし、損害賠償の範囲は、買主が瑕疵がないものと信頼したことより被った損害(いわゆる「信頼利益」)の範囲に限られることになります。
改正前民法における瑕疵担保責任の要件と効果
- 目的物に「隠れた瑕疵」が存すること
- 責任の内容は原則として損害賠償(信頼利益に対する賠償)
- 契約目的不達成の場合に限り契約解除可
- いずれの責任も売主の無過失責任
2. 改正民法の契約不適合責任の内容
改正民法では、改正前民法の瑕疵担保責任に代わり、いわゆる「契約不適合責任」に置き換えられることになりました。その理由は、目的物が契約の趣旨に適合しない場合は、特定物売買であったとしても、債務の不履行に該当するのではないか、という考え方によります。契約不適合責任においては、「瑕疵」や「隠れた」という概念は直接の要件とはされていません。改正民法における契約不適合責任では、客観的に瑕疵といえるか否か、それが隠れたものであるか否かを問題とするのではなく、引き渡された目的物がその種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか否かが問題になります。
改正民法では、契約不適合責任の内容としては、①履行の追完請求権(改正民法562条)、②代金減額請求権(改正民法563条)、③債務不履行の規定による損害賠償(改正民法564条)、④債務不履行の規定による契約解除(改正民法564条)が定められています。
(1)履行の追完請求
(2)代金減額請求
追完請求権(修補請求権等)、代金減額請求権は、債務の本来の内容の実現を求めるものですから、売主の過失は要件とされておりません。
(3)損害賠償と解除
① 契約不適合責任における損害賠償
② 契約不適合責任における契約解除
契約不適合責任に基づく解除は、債務不履行の一般原則と同様に、相当の期間を定めて催告し、催告期間内に履行されなければ契約を解除できるということになり、債務の不履行部分が軽微であるときは解除できないことになります。
江口 正夫
- 住まいの情報
- 住まいの税金・諸費用
- 住まいのお役立ち情報
- 住まいの法律知識
- 住宅の供給方式と契約類型
- 建物の建築段階での土地・建物売買契約の締結
- 借地権付住宅分譲と地主の承諾
- 住宅の買換え・下取り契約の法形式
- 自宅の土地建物の買換特約
- 売買契約書の印紙・印鑑・契印
- 売買契約に要する費用の負担
- 住宅売買契約における売買対象物の範囲
- 住宅売買契約と交渉預り金
- 不動産売買契約におけるローン条項
- 住宅ローン条項と指定機関外からのローン
- 住宅売買契約における手付解除とクーリングオフ
- 住宅売買契約における手付解除と「履行の着手」
- 代金支払いと登記・引渡し
- 不動産売買契約の解除が認められる場合
- 土地建物売買契約の売主の債務不履行責任
- 売買契約締結後の売主側の過失による建物の滅失
- 売買契約締結後の売主の破産
- 買主の資力と不動産業者の責任範囲
- 買主の代金支払債務の不履行と売主の対応策
- 住宅売買契約を締結した後の居住環境の変化
- 購入した住宅が設計・仕様書と異なる場合
- 不動産売主の契約不適合責任 ~瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
- 建売住宅の欠陥と買主の対応策
- 不動産売買契約と契約不適合責任免除特約
- 土地建物と不動産登記との関係
- 土地売買契約書に記載された土地面積の意義
- 不動産取引における登記事項の確認
- 宅地分譲と私道負担
- 道路予定地と売買契約締結の可否
- 袋地の通行権と接道義務の関係
- 購入した建物の敷地が越境していた場合の法的責任
- 住まいの保険知識
- 過去の住宅工事仕様書
- 住まいの法律知識
- 住まいの維持管理
- 調査・研究
- セミナー情報
- 住宅問題調査会
- 住宅・金融フォーラム