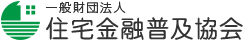か行
火災保険
瑕疵担保責任
改正前民法では、売買物件に「隠れた欠陥(=瑕疵)」が存在する場合は、売主は瑕疵担保責任を負うものとされ、瑕疵担保責任の内容は、①原則として損害賠償、②例外的に契約の目的を達しない場合に限り契約の解除が認められていた。
令和2年4月1日に施行された、改正民法では、改正前民法の瑕疵担保責任に代わり、「契約不適合責任」に置き換えられた。
令和2年4月1日に施行された、改正民法では、改正前民法の瑕疵担保責任に代わり、「契約不適合責任」に置き換えられた。
割賦元金
毎月の返済額のうち、元金の返済に充当される部分をいう。
割賦利息
毎月の返済額のうち、利息に相当する部分をいう。
借換え
新たなローンを借り入れて得た資金で、従前のローンを一括返済することをいう。
従前より低い金利のローンに借り換えることにより、支払利息の軽減を図ることが目的だが、ローン借換えに伴う諸経費(登記費用等)を考慮すると、期待するほど軽減効果を得られない場合もある。また、物件に対する担保評価もその時点で行われるため、担保割れしている場合には、借換えできない場合もある。
従前より低い金利のローンに借り換えることにより、支払利息の軽減を図ることが目的だが、ローン借換えに伴う諸経費(登記費用等)を考慮すると、期待するほど軽減効果を得られない場合もある。また、物件に対する担保評価もその時点で行われるため、担保割れしている場合には、借換えできない場合もある。
元金
借り入れたローンの融資金額(借入残高)。
元金均等返済
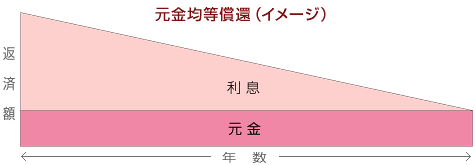
元利均等返済
毎回の返済額(元金と利息の合計)が同じ金額になるように返済していく方法で、元金均等返済に比べるとローン残高の減少スピードが遅いため、総支払利息は元金均等返済よりも増えるが、返済開始当初の返済額を少なくすることができ、返済計画は立てやすいという特長がある。
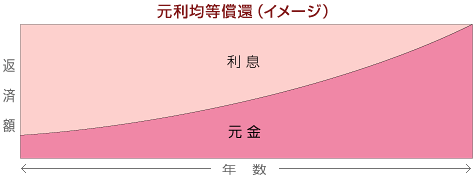
機関保証
保証料を支払うことによって保証会社が連帯保証人の役割を果たす制度。金融機関の系列会社が保証会社を運営していることが多い。(⇔自然人保証)
保証会社は、住宅ローン借入者が延滞等の約定違反により全額繰上償還請求を受けると、その残債務をローン借入者に代わって金融機関に対し支払い債務を精算するが、住宅ローン借入者はこれをもって債務が免除されるわけではなく、代位弁済した(してくれた)保証会社への返済義務を負うこととなる。
保証料は借入額が多いほど、また返済期間が長くなるほど高くなるが、保証会社によって料金が異なる。この保証料は、借入時に一括して支払う方法のほか、金利に保証料分を上乗せした形で支払う方法を選べるが、この場合0.2~0.3%程度融資金利が高くなる。
保証会社は、住宅ローン借入者が延滞等の約定違反により全額繰上償還請求を受けると、その残債務をローン借入者に代わって金融機関に対し支払い債務を精算するが、住宅ローン借入者はこれをもって債務が免除されるわけではなく、代位弁済した(してくれた)保証会社への返済義務を負うこととなる。
保証料は借入額が多いほど、また返済期間が長くなるほど高くなるが、保証会社によって料金が異なる。この保証料は、借入時に一括して支払う方法のほか、金利に保証料分を上乗せした形で支払う方法を選べるが、この場合0.2~0.3%程度融資金利が高くなる。
期限の利益
期限の到来までは債務の履行を請求されないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。
住宅ローンの場合では、約定期日までは返済請求を受けない(=分割返済を継続できる)ことが「利益」となるが、返済の遅延が続くなどして銀行等から全額繰上償還請求を受けた場合、この「期限の利益」は失われることとなる。
住宅ローンの場合では、約定期日までは返済請求を受けない(=分割返済を継続できる)ことが「利益」となるが、返済の遅延が続くなどして銀行等から全額繰上償還請求を受けた場合、この「期限の利益」は失われることとなる。
競売
債権者(抵当権者)が裁判所に抵当権を設定した不動産の競売を申し立て、債権の回収を図る法的(強制執行)手続き。
共有名義
住宅を購入する際に、複数人が出資した場合、その割合に応じて共有で登記をすることをいう。
金銭消費貸借契約
金融機関から融資を受けるときに交わす借入(ローン)契約のこと。
繰上返済(期間短縮型)
ローン残高の一部(または全額)を約定日前に返済することによって返済期間を短くすることをいい、もともと負担するはずだった支払利息を軽減できる。
一部繰上返済には、返済期間を変えずに毎月の返済額を減らす返済額軽減型もあるが、一般的には、期間短縮型の方が利息軽減効果が高い。
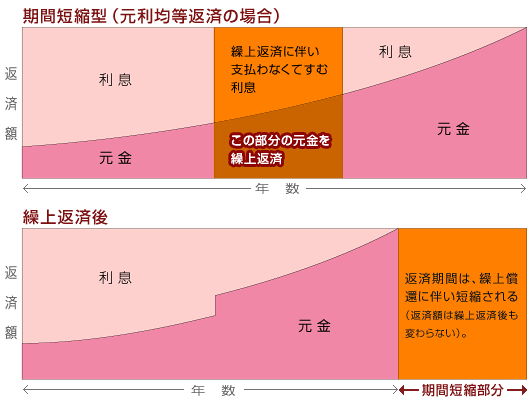
繰上返済(返済額軽減型)
ローン残高の一部を返済するが、返済期間は変えずにその後の返済額を減らす繰上返済の方法。
期間短縮型と同様に、利息軽減効果がある。
期間短縮型と同様に、利息軽減効果がある。
繰上返済手数料
契約不適合責任
令和2年4月1日に施行された、改正民法では、改正前民法の瑕疵担保責任に代わり、「契約不適合責任」に置き換えられた。契約不適合責任の内容として、①履行の追完請求権、②代金減額請求権、③債務不履行の規定による損害賠償、④債務不履行の規定による契約解除が定められている。
住宅の場合、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分に関しては、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)の施行により、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約(請負・売買)から、10年間の瑕疵担保期間が定められている。
なお、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅については、工事を請け負った建設会社、新築住宅を引き渡す場合の売主(不動産会社など)が、10年間の瑕疵担保責任を果たすよう保証金供託または保険加入による資力確保を義務付けられた。
住宅の場合、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分に関しては、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)の施行により、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約(請負・売買)から、10年間の瑕疵担保期間が定められている。
なお、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅については、工事を請け負った建設会社、新築住宅を引き渡す場合の売主(不動産会社など)が、10年間の瑕疵担保責任を果たすよう保証金供託または保険加入による資力確保を義務付けられた。
個人情報の保護に関する法律(抄)(平成15年法律第57号)
第1条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
個人信用情報
個人の属性(氏名、年齢、性別等)や返済能力(クレジットやローンの取引状況等)などに関する情報。
個人版民事再生
多重債務を抱え返済困難になった場合でも、将来において継続的な収入を得る見込みがあるときは、民事再生計画に「住宅資金貸付債権に関する特則」を設けた場合、かつ、裁判所から認可を受けた再生計画に基づいて3年間返済を継続することができれば、原則として、住宅ローン以外の借入金の残債務がすべて免除されるという制度。
自己破産の場合と異なり、保有財産(マイホーム等)を手放すことなく返済を継続していくことができるなどの特徴がある。
自己破産の場合と異なり、保有財産(マイホーム等)を手放すことなく返済を継続していくことができるなどの特徴がある。
固定金利型ローン
固定金利期間選択型ローン
ローン実行時から一定期間の金利を固定するタイプのローン。
金利を固定できる特約期間は金融機関によって異なり、2年、3年、5年、7年、10年などが選べる。当初選択した固定金利期間が終了すると、金融機関によって、(1)再度、固定金利型か変動金利型かを選択できる、(2)変動金利型しか選択できない、などの違いがある。
金利を固定できる特約期間は金融機関によって異なり、2年、3年、5年、7年、10年などが選べる。当初選択した固定金利期間が終了すると、金融機関によって、(1)再度、固定金利型か変動金利型かを選択できる、(2)変動金利型しか選択できない、などの違いがある。
固定資産税
毎月1月1日現在で、各市町村税務課(東京23区の場合は都税事務所)の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金(地方税)。
固定資産税評価額
3年に1度、知事または市町村長が固定資産評価基準に基づいて評価した価額のことで、土地課税台帳または家屋課税台帳に記載される価額。
一般的には、土地は時価の70%程度、建物は建築費の50~70%程度の価額になるといわれている。
一般的には、土地は時価の70%程度、建物は建築費の50~70%程度の価額になるといわれている。
コンプライアンス
【英】compliance
日本語で「コンプライアンス」という場合、法令の順守や、企業倫理・経営倫理との関連で論じられることが多い。一般的には、「社会秩序を乱す行動や社会から非難される行動をしないこと」と解釈されている。
日本語で「コンプライアンス」という場合、法令の順守や、企業倫理・経営倫理との関連で論じられることが多い。一般的には、「社会秩序を乱す行動や社会から非難される行動をしないこと」と解釈されている。