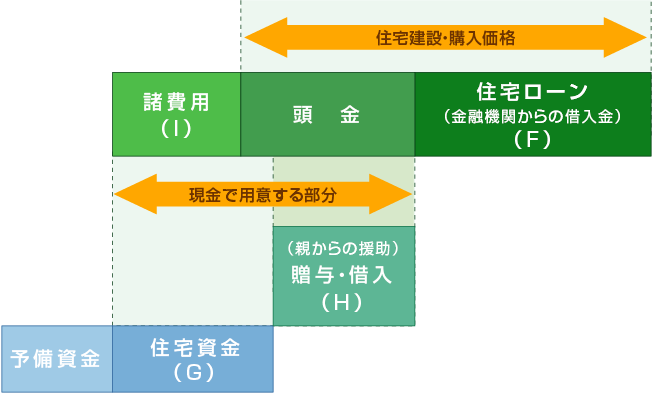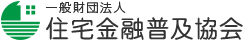住宅ローンの特徴と資金計画におけるポイントや解説を参考に、自分に合った住宅ローンを選びましょう。
point
- 住宅の建設費(購入価格)だけでなく、諸費用※を含めた総費用を把握しましょう
- 総費用の2~3割程度の現金は準備しましょう
- 『借りられる金額』ではなく『無理なく返せる金額』を借入額にしましょう
- 金利水準やライフプランを考慮して、家計に合った金利タイプや返済期間などの住宅ローンを選びましょう
※諸費用とは住宅ローン利用時に必要な事務手数料、ローン保証料などの諸費用の他、不動産取得税等の税金や不動産仲介手数料、引越し代など住宅取得に伴って必要となる費用のことです。
1. 住宅ローンを比較し検討しましょう
Qすすめられた提携ローンで大丈夫ですか?
Aすすめられた提携ローンだけでなく、他のローンについても検討しましょう。
すすめられた提携住宅ローンが家計にあった住宅ローンとは限りません。
住宅ローンは、さまざまな金融機関で取り扱っており、住宅ローン商品の種類も豊富です。すすめられた提携住宅ローン以外のローンも選ぶことができます。幅広くライフプランにもあった住宅ローンを選びましょう。
point
- 複数の金融機関、住宅ローン商品について検討しましょう。
- 住宅ローンはすすめられた提携ローン以外のローンも選択できます
2. 総支払額で比較・検討しましょう
Q金利が一番低ければ、総支払額も一番低いのですか?
A金利だけでなく、事務手数料や保証料などの諸費用を含めた総支払額でも比較・検討しましょう。
当初金利が低ければ、当初のローンの返済総額は低くなります。しかし、変動タイプの住宅ローンを選択した場合、金利が変動するかどうかで総支払額は大きく変わります。また、住宅ローンでは、事務手数料や保証料などが必要ですので、総支払額でも比較、検討することが必要です。
point
総支払額は次の計算式で求めましょう
ローンの返済総額+(事務手数料+保証料+団体信用生命保険料等の諸費用)= 総支払額
総支払額を比較してみましょう
金利が低くて事務手数料が高い場合と事務手数料が低くて金利が高い場合を比べてみます。このほかにも保証料、団体信用生命保険料等の諸費用が必要な場合は、加えて検討する必要があります。
借入額3,000万円、返済期間35年、元利均等返済、ボーナス併用返済なし、
返済期間中に金利が変動しない場合
| 金利 | 事務手数料 | 毎月の返済額 | 総支払額※ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1.95% | 借入額×2.2% | 660,000円 | 98,610円 | 42,076,359円 |
| ② | 2.00% | 定額 | 55,000円 | 99,378円 | 41,793,968円 |
| ①-② | 605,000円 | △768円 | 282,391円 | ||
①の方が金利が低く、毎月の返済額も少ないのですが、事務手数料が高いので総支払額は②の方が少なくなります。
※表中の総支払額は、毎月の返済額を返済終了まで合計したローンの返済総額と事務手数料を足した額です
3. 借入れ後の利便性も確認しておくと安心です
Q借入れ後の利便性ってなんですか?
A繰上返済や返済中の条件変更など住宅ローンの見直しやすさをいいます。
ローン返済総額を少なくするために繰上返済を行ったり、返済が苦しくなった場合に返済条件の変更を行い返済額を減額したり、借入れ後にも返済計画を定期的に見直すことが重要です。
住宅ローンを選ぶ際には、借入れ後の利便性について柔軟に対応できるかどうかを確認しておくと安心です。
point
利便性の確認事項
- 繰上返済の手続きの時期(いつまでに申し出る必要があるか)、手続き方法(インター ネット、来店など)、繰上返済がいくらから申込みできるか、繰上返済手数料など
- 金利のタイプの変更、返済期間の延長など返済計画の見直し(条件変更)ができるか
4.「無理なく返せる額」を試算しましょう
| 毎月の「住宅関係費」はいくら? | |
|---|---|
|
+
=
※ボーナス払い分も含め、年間支払額の1/12で試算しましょう。 |
万円(A) |

| 住宅取得後の維持費等は1か月いくら? | |
|---|---|
| ① 固定資産税・都市計画税(月割) |
万円 |
| ② 火災保険・地震保険(月割) |
万円 |
| ③ マンション → 管理費・修繕積立金 一戸建て → 将来の修繕費 ※1 |
万円 |
| ④ 駐車場・駐輪場代 |
万円 |
| ⑤ 光熱費等の増加分など※2 |
万円 |
| ⑥ 計画的貯蓄(月割)※3 |
万円 |
| 合計 |
万円(B) |
※1 一戸建ての場合、管理費・修繕積立金はありませんが、将来かかる修繕費用などを見越して計画的に準備しておくと安心です。
※2 持ち家の場合、従前の住宅よりも床面積が広くなり、床暖房などの設備が加わることが多く、光熱費が1~2割程度増加することを見込んでおくと安心です。
※3 住宅取得後、予測される子供の養育費用、教育資金、車の買替え資金、老後資金などのライフイベントに備えるための貯蓄は重要です。

| 無理なく返せる毎月の返済額 | |
|---|---|
| (A)-(B) |
万円(C) |

| 返し続けられる年数は? | |
|---|---|
|
-
=
|
年間(D) |

| 無理なく返せる借入額は? |
|---|
| 【住宅ローンシミュレーション】「借入可能額の計算」で試算 |
【住宅ローンシミュレーション】「借入可能額の計算」で試算するときの入力データ
※1 借入金利は、当初の金利を入力します。なお、実際の借入にあたっては当初期間終了後の金利変動に伴う返済額の増減について注意が必要です。
※2 返済負担率は本試算上Step3の無理なく返せる毎月の返済額(C)から自動計算するため入力はできません。
「住宅ローンシミュレーション」「借入可能額の計算」では入力可能です。
5. 適正な住宅取得予算を試算しましょう
| 「借り入れできる額」 | |
|---|---|
| Step5の(E)の「無理なく返せる借入額」と「金融機関からの借入可能額」のいずれか小さい額を記入 |
万円(F) |

| 貯蓄のうち住宅取得にまわせる額は? |
万円(G) |
|---|

| 両親など親族から資金援助が受けられる額は? |
万円(H) |
|---|

| 諸費用分は? | |
|---|---|
| {(F)+(G)+(H)}× 5 ~ 10% |
万円(I) |

| 適正な物件の予算は? | |
|---|---|
| (F)+(G)+(H)-(I) |
万円 |
【住宅取得予算】イメージ図