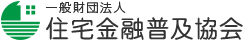高齢になると筋力や感覚が衰えて、住み慣れた自宅であっても、少しの段差でつまずいたり、何気ない動作でバランスを崩しやすくなります。
高齢者の家での事故を予防し、介護が必要になった際は介護が必要な方、介護をする方双方が安心して快適に暮らしていくために、バリアフリーリフォームや在宅介護リフォームを考える必要があります。
高齢者の家での事故を予防し、介護が必要になった際は介護が必要な方、介護をする方双方が安心して快適に暮らしていくために、バリアフリーリフォームや在宅介護リフォームを考える必要があります。
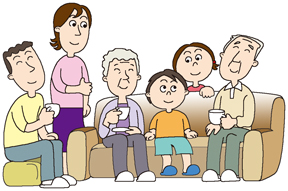
バリアフリーリフォーム
住まいのリフォームで、つまづきを防ぐため床の段差を解消すること、床に滑らない素材を使用すること、手すりをつけて歩きやすくすること、車椅子などの補助器具を使えるようにすることなどを「バリアフリーリフォーム」と言います。



バリアフリーリフォームを対象とした税の優遇制度
バリアフリーリフォームを対象とした税の優遇措置があります。詳しくは、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会の「リフォーム減税制度」等の資料をご確認ください。
参考サイト
在宅介護リフォーム
「バリアフリーリフォーム」の中で、特に住まいで浴室やトイレに自力で行けるように、また、介助する側の負担も軽減できるよう“住まいの中での介護”という視点で行うリフォームのことを言います。
「在宅介護リフォーム」は2000年に始まった介護保険制度等と大きく関わっています。
「在宅介護リフォーム」は2000年に始まった介護保険制度等と大きく関わっています。
介護保険制度
介護保険制度は2000年にスタートしました。
介護保険サービスは、65歳以上の方であれば、原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40~64歳の方は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態となったときに受けることができます。
介護や支援が必要になった場合、住所のある市・区役所、町村役場に「要介護認定」の申請をして、介護認定審査会にどの程度の介護、支援が必要かを認定してもらいます。
介護保険の助成金は、リフォーム工事が完了して、リフォーム業者に工事代金を全額支払った後に、介護保険改修費支給申請書と添付書類を市区町村に提出することにより、支払われます。
介護保険サービスは、65歳以上の方であれば、原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40~64歳の方は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態となったときに受けることができます。
介護や支援が必要になった場合、住所のある市・区役所、町村役場に「要介護認定」の申請をして、介護認定審査会にどの程度の介護、支援が必要かを認定してもらいます。
介護保険の助成金は、リフォーム工事が完了して、リフォーム業者に工事代金を全額支払った後に、介護保険改修費支給申請書と添付書類を市区町村に提出することにより、支払われます。
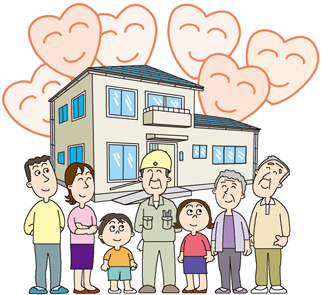
参考サイト
「在宅介護リフォーム」を考えるポイント
- 介護を受ける方が望むレベル、そして現状の身体機能のレベルを明確に分析すること。
- 介護を受ける側とする側の双方の希望や介護しやすさを確認し、最もよい解決策を探すこと。
- 要望をまとめた時点で、改修工事内容・建築条件・費用等について、必ず専門家のアドバイスを受けること。
- 介護保険制度の活用について、事前にケアマネージャー(介護支援専門員) などに確認すること。
- 自治体独自の助成金など(高齢者住宅改修費支援制度や障害者住宅改造費助成制度など)が用意されているかどうかを自治体の相談窓口に確認すること
専門家のアドバイス
在宅介護の専門家である、ケアマネージャー(介護支援専門員)、福祉住環境コーディネーター、医療関係者などにアドバイスをもらいましょう。
既に介護を受けている方の場合には、介護を担当しているホームヘルパーなどの意見も貴重です。
次に、改修工事を行う建築の専門家にもアドバイスをもらうことが大切です。介護を目的としたリフォームはかなり特異性があるので、出来れば、既に在宅介護リフォームの実績のある設計者やリフォーム業者などに話を聞くようにしましょう。
介護保険金制度を使ったリフォーム
介護保険制度では、「要支援」または「要介護」と認定された方のうち、在宅で、かつ住宅改修が必要な人に対し、住宅改修費の20万円を上限に工事の内容などに応じて最大9割までの給付が受けられます。
| (1)手すりの取付け | 屋内の玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などに設置する手すりに適用される他、建物の出入り口から道路までの屋外手すりも対象となります。 |
|---|---|
| (2)段差の解消 | 敷居や引き戸レールなどをフラットにしたり、玄関や浴室、出入り口などの段差をスロープや踏み台、床のレベル調整工事などにより解消する場合に適用されます。 |
| (3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 | 歩行時に滑りやすい床、車イスが利用しにくい平滑ではない床(畳床など)を、滑りにくい床、フローリング床、固い床材などに変更する場合に適用されます。 |
| (4)引き戸等への扉の取替え | 車椅子使用時には開閉が困難になる開き戸を、引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなどに変更する場合、また、高齢で力が弱い方、手首などの怪我により一時的に握力が低下している人などでも操作し易いドアノブや動きの軽い戸車の設置などの場合にも適用されます。 |
| (5)洋式便器等への便器の取替え | 和式便器から洋式便器への交換や、介護上、便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替えなどに適用されます。 |
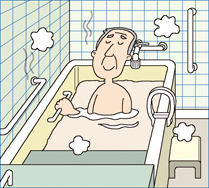

ご注意
- 注意したいのは、介護保険で助成される助成金は、リフォーム工事完了後、一旦、工事業者に消費者が工事代金を全額支払った後に、介護保険改修費支給申請書と添付書類を市区町村に提出することになっていて、申請書が受理されると介護保険金が支給されます。
- つまり、添付書類に不備があった場合などは、住宅改修費が支給されないというケースも発生しますので、注意が必要です。
- 更に、保険申請者が高齢であることから、そこにつけこんで法外な工事費を請求してきたり、勝手な契約書を作成してくるというケースも多々ありますので、必ず、自身だけの判断で話を進めるのではなく、相談することを忘れないようにしてください。
- 消費者センターや国民生活センターに寄せられる住宅改修に関する相談は、年々増加傾向にあることからも、消費者自身が充分に注意をすることが大切です。
要介護状態等区分と保険給付
要介護状態等区分に応じて、在宅の場合には支給限度額、施設の場合には保険給付額がそれぞれ決められます。要介護認定等の判断基準は、介護保険の給付額に関係するため、全国一律に定められています。
要介護状態等区分の目安
要支援者は、身体・精神障害により、6か月にわたり、継続して日常生活の一部に支障がある状態にある方です。
| 要支援1 |
|
|---|---|
| 要支援2 |
|
要介護者は、身体・精神障害により、6か月にわたり、日常生活動作の一部または全部に介助を必要としている状態にある方です。
| 要介護1 |
|
|---|---|
| 要介護2 |
|
| 要介護3 |
|
| 要介護4 |
|
| 要介護5 |
|
参考サイト
公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット
介護保険金制度を使ったリフォームの流れ
①住宅改修についてケアマネジャー等の専門家に相談する

②申請書類又は書類の一部提出・確認
- 利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者(市町村及び東京都特別区、以下同じ)へ提出
- 保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)- 支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)

③施工→完成

④住宅改修費の支給申請・決定
- 利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出 「正式な支給申請」が行われる。
- 保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、 当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
- 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※やむを得ない事情がある場合は、④の段階において②の書類等を提出することができる。
参考サイト
60歳以上の方への住宅ローン
「リ・バース60」は、満60歳以上のお客さま向けの住宅ローンです。毎月のお支払は利息のみで、元金は、お客さまが亡くなられたときに、相続人の方から一括してご返済いただくか、担保物件(住宅および土地)の売却によりご返済いただくことができます。
「リ・バース60」は、住宅の建設、購入、リフォーム、 借換えにご利用いただくことができます。
参考サイト
在宅介護リフォーム等の相談窓口
リフォームでお困りのことや分からないことは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」で電話相談を受けることができます。
電話相談では、専門の相談員(建築士)が電話で対応してくれます。また対応する建築士は財団に常駐する弁護士の助言を受けながら、法的な諸問題に関しても幅広くアドバイスをしてくれます。
電話相談では、専門の相談員(建築士)が電話で対応してくれます。また対応する建築士は財団に常駐する弁護士の助言を受けながら、法的な諸問題に関しても幅広くアドバイスをしてくれます。